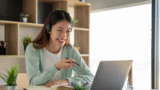「DX」という言葉が飛び交う今、多くの企業がデジタルツールを導入するものの、真の変革を実感できていないのではないでしょうか。
その中で、経済産業省から「DXプラチナ企業」に選定されるなど、製薬業界のDXを牽引する中外製薬。彼らがデジタル変革で圧倒的な競争優位性を築けている理由は何でしょうか?
単なる業務効率化にとどまらず、彼らはAIやデジタル技術を使いこなす人材を戦略的に育成することで、イノベーションを次々と生み出してきました。
日本の製薬業界にはトップクラスの売上を誇る企業が他にもありますが、中外製薬は利益率と時価総額で業界トップを維持しています。これは、DXを成長戦略の核に据え、全社を挙げて変革を推進してきた結果にほかなりません。
本記事では、テクノロジーと組織変革の専門家の視点から、中外製薬のDXジャーニーを紐解き、特に人材育成における取り組みを詳しく解説していきます。
中外製薬とは?DX戦略の全体像
中外製薬は、革新的な医薬品開発に強みを持つ日本の大手製薬企業です。特にがん領域で世界的評価を受け、ロシュとの提携によりグローバル展開を加速しています。
中外製薬は研究開発から生産、販売に至るまでデジタル変革を積極的に推進しています。創薬の領域では、AIやシミュレーション技術を用いた創薬ターゲット探索や抗体エンジニアリングの効率化により、臨床試験の成功確率を高めています。また、リアルワールドデータやゲノム情報を活用した個別化医療の開発、さらにサプライチェーンや営業活動のデジタル化による生産性向上も進んでおり、これらのDX基盤が革新的新薬の創出やグローバル展開を後押ししています。結果として、投資家は単なる「新薬の期待」だけでなく、「DXを活用した持続的な研究開発力」を評価し、株価上昇につながっています。

本記事投稿日2025/9/23までの株価推移
中外製薬は、成長戦略「TOP I 2030」のKey Driverの一つとしてDXを明確に位置づけ、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げて全社DXを推進しています。
DX戦略である「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」では、「デジタル技術によって中外製薬のビジネスを革新し、社会を変えるヘルスケアソリューションを提供するトップイノベーターになる」という指針を定めています。その達成に向けて、以下の3つの柱を定義しています。
- デジタルを活用した研究・開発早期フェーズの高度化
- 全バリューチェーンにおける飛躍的な生産性向上
- イノベーション創出を支える全社基盤の構築
全社におけるデジタル人材の育成は、主にこの「イノベーション創出を支える全社基盤の構築」の取り組みとして位置づけられています。
中外製薬のDXにおける人材育成の取り組み
中外製薬の成功は、単なるITツールの導入に留まらず、全社的な文化と組織を根本から変革する包括的なアプローチにあります。中でも、特に注目すべき3つの取り組みを紹介します。
1. ハイブリッド人材の育成:「CHUGAI DIGITAL ACADEMY(CDA)」
中外製薬は、DXを「全社ごと」として捉え、全社員を対象としたデジタル人材育成プログラム「CHUGAI DIGITAL ACADEMY(CDA)」を設立しました。このプログラムの最終的な目標は、「ビジネス視点とデジタルスキルのハイブリッド人材」を育成することです。
たとえば、医薬品情報担当者(MR)が新しいアプリを使うだけでなく、そのアプリが医師や患者にどのような新しい価値をもたらすかを考えられるようになること。研究者がAIを活用して新薬の探索を行うだけでなく、そのプロセス全体を効率化する仕組みを自ら考案できるようになること。CDAは、このような自律的な行動を促すことを目指しています。
CDAのコンテンツ設計は、以下の3つのポイントが特徴です。
- 全社員を対象とした基礎コース:全社員がデジタル知識の基礎を習得できるよう設計されており、特にeラーニング「CDA Essential」は、「学びたい人が誰でも学べる」をコンセプトに全社員に公開されています。
- 専門人材の育成:データサイエンティストなどの専門家を育成するための選抜型プログラムも用意。スキル標準を活用し、DX推進の核となるビジネスアーキテクトやデータサイエンティストを優先的に育成しています。
- 階層別研修:スタッフ、マネージャー、役員といった各階層に合わせたアプローチを取り、デジタルプロジェクトのリーダーなどの重要な役割に焦点を当てています。
このCDAにご興味ある方は、ぜひグロービスのインタビュー記事「2023/7 DXグランプリ企業「中外製薬」のデジタル人財育成と風土改革とは」を確認ください。
2. ボトムアップのイノベーション:CHUGAI RPAとDigital Innovation Lab
中外製薬のDXを深く支えているのは、社員一人ひとりのアイデアを吸い上げ、形にする仕組みです。
– 「CHUGAI RPA」市民開発イニシアティブ:プロジェクトからムーブメントへ
2018年に始まったRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の取り組みは、「年間10万時間の業務削減」という壮大な目標を達成しました。その成功は、単なるツールの導入ではなく、RPAに対するユニークな「考え方」と「アプローチ」にありました。
- RPAを再定義:RPAを「Robotic Process Automation」ではなく、「Reconsider Productive Approach(生産的アプローチの再考)」と再定義。ロボット開発の前に、業務プロセスそのものの見直しを徹底しました。
- 「困りごと」から始める:現場に「自動化したい業務」ではなく、「困っている業務」を問いかけることで、ツールありきではない本質的な課題解決を促しました。
- 全社に計画書を課す:トップダウンで各部門に「RPA活動推進計画書」の作成を義務化。これにより、RPAが全社員にとって「自分ごと」となり、健全な競争意識が生まれました。
- 「苦労体験」を共有:成功事例だけでなく、運用後の失敗談やトラブルシューティングのノウハウを積極的に共有。組織全体に現実的な知見が蓄積されました。
- 目標を「1%」に翻訳:壮大な「10万時間」の削減目標を、全社員の年間総就労時間の「約1%」と表現。これにより、巨大な目標が個人にとって達成可能なものとなりました。
これらの取り組みの真の価値は、単なる生産性向上効果に留まりません。社員自身がRPAを開発できる「社内認定制度」や、RPA推進コミュニティ内の助け合いを促進する社内アプリ「Help me help you」、アイデア収集の「RPA IDEA BOX」や教育プログラム「CHUGAI RPA Square」など、具体的な仕組みが文化を後押ししました。さらに、「RPA Award」という表彰制度が社員のモチベーションを高めています。
こうした多角的な取り組みにより、RPAは中央主導のプロジェクトから、従業員主体のボトムアップ文化へと進化し、プログラムの持続可能性を保証する、深い文化的変革へとつながったのです
– Digital Innovation Lab (DIL):アイデア発掘の正式なチャネル
「イノベーションを創出せよ」というスローガンだけでは、社員の主体性は生まれない。中外製薬は、「Digital Innovation Lab(DIL)」という具体的な仕組みを構築することで、社員一人ひとりのアイデアを形にするための「インフラ」を提供している。
この仕組みが単なる“ガス抜き”で終わらないことは、その制度設計と具体的な成果を見れば明らかだ。DILは、ボトムアップでのイノベーションを加速させるため、以下の特徴を持つ。
- 全社員が上司の許可不要で応募可能:伝統的な階層組織における最大の障壁を取り払い、心理的安全性を確保。
- PoC(概念実証)の費用を会社が拠出:失敗を恐れず挑戦できる環境を提供し、早期段階のイノベーションを体系的に支援。
- アイデア創出から企画書作成までをワークショップで支援:アイデアを事業化するプロセスを伴走支援。
このインフラの結果、2020年の開始以来450件以上の応募が寄せられ、約60件がPoC(概念実証)を実施、そのうち20件が本番開発へと移行している。数字以上に重要なのは、参加者の約9割が「変革意識が向上した」と回答している点だ。DILはアイデアを事業化するだけでなく、社員の「主体性」を育む、風土改革のエンジンそのものなのだ。
3. 生成AIの全社展開:人がより良いことをやるためのバディへ
中外製薬は、生成AIの活用を単なる「効率化」に終わらせず、「人がより良いことをやる」ためのバディ(パートナー)としてAIを活用し、イノベーションを生み出すことを目指しています。
生成AI活用に向けたビジョンを策定し、全社横断の推進体制を構築。人材育成を含めて各部門への導入・開発を支援しています。具体的な取り組みは以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 全社トライアル | ChatGPTについて全社で数百名規模のトライアルを実施中。各部門のアイデアを集約し、共通化できるものは全社ツールとしてインターフェース作成を含めて開発・実装しています。 |
| 導入フェーズ | 導入の最初のステップとして、全社員が「怖い」といったバイアスをなくすため、生成AIを簡単に使える環境を用意しました。まずは仕事でもプライベートでも「使って遊んでみる」ことを促し、次に仕事での応用シナリオを共創する伴走型のアプローチをとっています。 |
| R&D領域の価値創出 | 研究者が持つバイアスを取り払い、人間が思いつかないような化合物を考えるために生成AIを活用しています。研究者は生成AIを壁打ち相手として使い、より良いものを選択していくことができます。 |
| バリューチェーンの効率化 | MR(営業)のドクターとの会話シミュレーションに生成AIを活用した事例があります。AIが製薬業界の営業ルール(説明責任、コンプライアンス等)をチェックし、採点まで行うことで、短期間でのトレーニングが可能になりました。 |
中外製薬の生成AIの取り組みについて、詳細を知りたい方はぜひ以下のPIVOTの動画をご覧ください。
このように中外製薬のデジタル人材育成の主要な取り組みをご紹介しましたが、実際にはその他にも、海外交流プログラムや社外実践研修(留職プログラム・越境プログラム)など、多角的な人材育成策が展開されています。このような人材育成の取り組みについては、ぜひ中外製薬の人的資本レポートをご確認ください。
DXを牽引するトップダウンのリーダーシップ
中外製薬のDX成功は、強力なトップリーダーシップなくしては語れません。元IBM出身の上席執行役員である志済聡子氏は、自身の役割をIT部門長ではなく「DXの旗振り役」だと明確に認識。DX推進における組織的な障壁を排除するため、IT部門とDX部門を統合するという大胆な組織再編を断行しました。
この変革プロセスは、「フェーズ1:人・文化を変える」(2021年に完了)と「フェーズ2:ビジネスを変える」(2024年が最終年)という、明確な段階的アプローチに基づいて進められました。これは、まず従業員の意識と文化を根本的に変革し、その上でビジネス成果を追求するという、意図的で順序立てられた戦略を示しています。
まとめ: DXの本質は「変革のDNA」を植え付けること
中外製薬が示してくれたのは、DXが単なる「デジタル化」ではないということです。それは、AI時代の未来を見据え、組織全体が自律的に進化し続けるための「変革のDNA」を植え付けるプロセスにほかなりません。
私たちがDX Change Labで一貫して伝えてきたように、DX成功の鍵は、一部の専門家だけが担うプロジェクトではなく、全社員が「自分ごと」として捉え、行動する文化を築くことにあります。中外製薬の取り組みは、その理想的な実践例と言えるでしょう。
このブログ記事が、あなたの組織に眠るDXの可能性を解き放つ、最初の一歩となることを願っています。
サムネイル画像クレジット:geraltによるPixabayの画像
参考情報:
- https://www.chugai-pharm.co.jp/innovation/digital/vision.html
- https://www.chugai-pharm.co.jp/innovation/digital/platform_value_chains.html
- 中外製薬 2023/11 ビジネス視点とデジタルスキルのハイブリット人材
- 2023/7 中外製薬 Generative AI活用への取り組みと人財強化の方向性
- 2023/7 DXグランプリ企業「中外製薬」のデジタル人財育成と風土改革とは
- 2021/6 中外製薬 定型業務のAI化等で21年は5万時間、23年は10万時間の業務削減達成へ「DX2030の絵姿」
- 参加社員約9割のDX取組み意識が向上。中外流、ボトムアップの公募制のアイデア実現プログラム『DIL』
- 2024/12 生成AIの全社活用を目指して-中外製薬が取り組む内製と協働による基盤構築
- 中外製薬、DX推進で生成AI活用9割超・LLM利用半数超 短期間で成果を出せた理由
- 第9回 900のアイデアを原動力に――中外製薬が実践する生成AI活用とは【前編】
- 第9回 900のアイデアを原動力に――中外製薬が実践する生成AI活用とは【後編】
- 志済聡子が語る成果と新たな挑戦・展望とは
- 中外製薬が本気で取り組む「中外流RPAの極意」