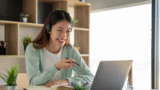「自分の仕事はいつかAIに奪われるのではないか」。
最近の大学卒業生や社会人になったばかりの若手にとって、この不安はもはや他人事ではありません。しかし、これは単なる未来への懸念ではないかもしれません。米国の労働市場データは、2022年後半から若年層全体の失業率が安定しているにもかかわらず、大卒直後の若者の失業率だけが急上昇しているという、不穏な兆候を示しています。
この静かな変化の背後で何が起きているのか。
ハーバード大学の研究者による最新の論文『Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data』(Hosseini & Lichtinger, 2025)が、具体的なデータでその実態を明らかにしました。
本記事では、この研究が暴いた、特にキャリアのスタートラインに立つ若手(ジュニア層)の雇用に関する5つの衝撃的な真実を、分かりやすく解説していきます。
AIがキャリアに与える影響を初めて大規模データで検証
この論文は、AIが「若手(ジュニア)」と「経験者(シニア)」にどんな影響を与えているかを初めて大規模なデータを使用し検証しました。
使用した米国の大規模な履歴書・求人情報データ
- 2015年から2025年までの約6,200万人の労働者
- 28.5万社に及ぶ
また、AIの影響を測るために、単なる「AIへの露出度」ではなく、企業が実際に「AIインテグレーター」の求人を出したかという具体的な行動指標でAI導入を特定。
AIインテグレーターとは、 AIシステムを企業に統合する専門家、例えば大規模言語モデル(LLM)の構築やAPI連携を担う役割
消えるキャリアの第一歩:AIは「年功序列」で若手を狙い撃ちにする
この研究が明らかにした最も衝撃的な事実は、生成AIの導入が「シニアリティ・バイアス(seniority-biased)」、つまり経験年数が多い人を優位に扱う傾向です。
データによると、AI導入企業は非導入企業と比較して、6四半期後(1年半後)には若手従業員の数が7.7%も少なくなっていました。
この発見が重要なのは、AIが単に特定のタスクを自動化するだけでなく、キャリアの階層構造そのものを変質させている可能性を示唆している点です。これまで若手が担ってきた定型的な業務がAIに代替されることで、社会人としての「キャリアの最初の⼀歩」を踏み出す機会そのものが浸食され始めているのです。
一体AIはどのように若手従業員の仕事を奪ったのでしょか?
解雇ではなく、「採用停止」:本当の脅威は企業の入り口で起きている
多くの人が「AIによる失業」と聞くと、今いる従業員が解雇される姿を想像するかもしれません。しかし、研究が示した現実はそれとは異なります。
人員の数の変動の原因は三つの可能性があります:
- 新規採用
- レイオフや離職
- 内部の昇進
データによりますと、AI導入企業は、若手従業員を解雇したわけではありません。ではなぜ若手従業員の数が減ったのか?
それは離職率の上昇やレイオフではなく、新規採用の大幅な縮小によって引き起こされていました。
実際に、AIを導入した企業は2023年第1四半期以降、非導入企業に比べて若手の採用を平均で約22%も削減していたことが明らかになりました。
この点は、脅威の本質を理解する上で極めて重要です。多くの人が恐れる「今ある仕事の喪失」以上に、「これからキャリアを始める人たちの入り口が静かに閉ざされていく」という変化の方が、より深刻な問題なのかもしれません。
昇進のパラドックス:社内にいる若手には追い風か?
新規採用が凍結される一方で、研究はもう一つの驚くべき事実を明らかにしました。それは、すでに社内にいる若手従業員の昇進が増加しているという点です。
AI導入企業では、四半期ごとに若手社員からシニア職への昇進が、非導入企業に比べて平均で0.4件多く発生していました。
これは、AIがエントリーレベルのタスクを代替したことで新規の若手需要が減る一方で、組織に残った経験豊富な若手の価値が相対的に高まった可能性を示唆している。
AIが狙う「中堅」の若者たち:衝撃の学歴別格差
AIの影響は、すべての若者に平等に訪れるわけではありませんでした。
本研究は、アメリカの大学を質や名声で5段階に分けて分析しました。Tier 1はハーバードのような最上位校、Tier 5は下位校としています。この分析から、AIによる雇用の減少が特定の層に集中していることが明らかになりました。
最も大きな打撃を受けたのは、最上位のエリート大学(Tier 1)や下位の大学(Tier 4, 5)の卒業生ではありませんでした。最も影響が大きかったのは、それに続く「優秀な(Tier 2)」および「堅実な(Tier 3)」と評価される、中堅上位の大学の卒業生だったのです。
この現象の背景には、企業側の合理的な判断があると考えられます。エリート層は、その高い生産性によってAIの代替から守られる傾向にあります。一方で、下位層の卒業生は、人件費の安さが強みとなり、雇用の機会が維持されやすいのです。しかし、中程度のコストとスキルを持つ「中間層」は、AIによる代替の波に最も激しくさらされ、競争の矢面に立たされているのです。
IT業界だけの話ではない:最も若手採用を減らした意外なセクター
最後に、この問題がテクノロジー業界だけのものではないことを示す、決定的なデータが示されました。若手の採用削減が最も顕著だったのは、多くの人が想像する業界ではありませんでした。
若手の採用削減は幅広いセクターで見られましたが、その中でも最も大きな減少(非AI導入企業に比べて約40%減)を記録したのは、「卸売・小売業(Wholesale and Retail Trade)」だったのです。
これは、卸売・小売業における若手のタスク(定型的なコミュニケーション、顧客対応、文書作成など)が、生成AIによって代替されやすいためと考えられる。
結論:AI時代におけるキャリア形成と組織の役割
本研究が明らかにしたのは、生成AIが単に仕事を奪うだけでなく、「キャリアのあり方」そのものを根本から再構築しているという事実です。この新しい現実は、私たち全員が向き合うべき課題を示唆しています。
個人として、これからのキャリアをどのように築くかが問われます。「言われたことをこなす人」から、AIを使いこなし、プロンプトを設計し、複雑な問題解決に貢献できる人材へと、スキルセットをシフトさせることが求められます。自らのキャリアを自律的にコントロールするために、AIをツールとして活用する能力を磨くことが不可欠です。
一方、DX推進者は、この変化を組織と人材の成長の機会として捉えるべきです。AIとの協業を前提とした新しい職務を設計し、それに適した人材の育成・採用戦略を立てましょう。単にAIツールを導入するだけでなく、AIと共存・共創する能力を育むリスキリングプログラムを従業員に提供することが重要です。
AIは、若手のキャリアの「入り口」を狭める可能性がありますが、同時に、社内の若手の「昇進の速度」を加速させる可能性も秘めています。AIを正しく理解し、戦略的に活用することが、この構造的な変化の時代を乗り切るための鍵となるでしょう。